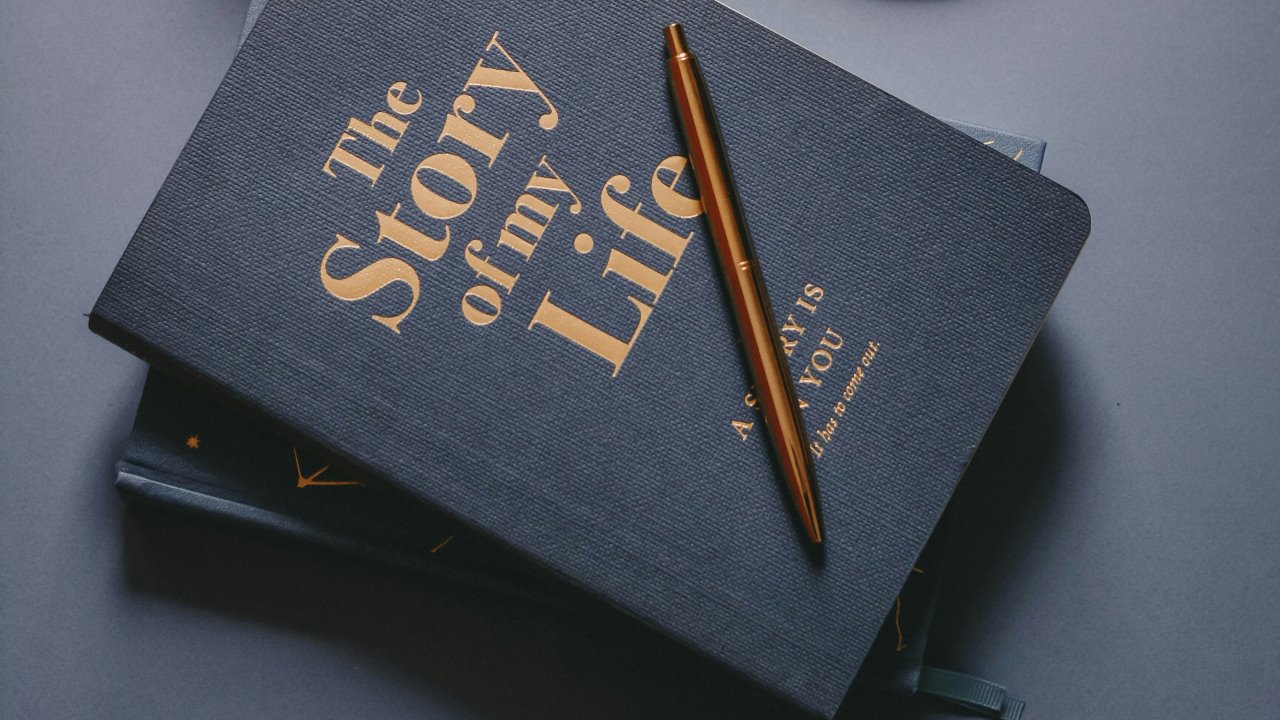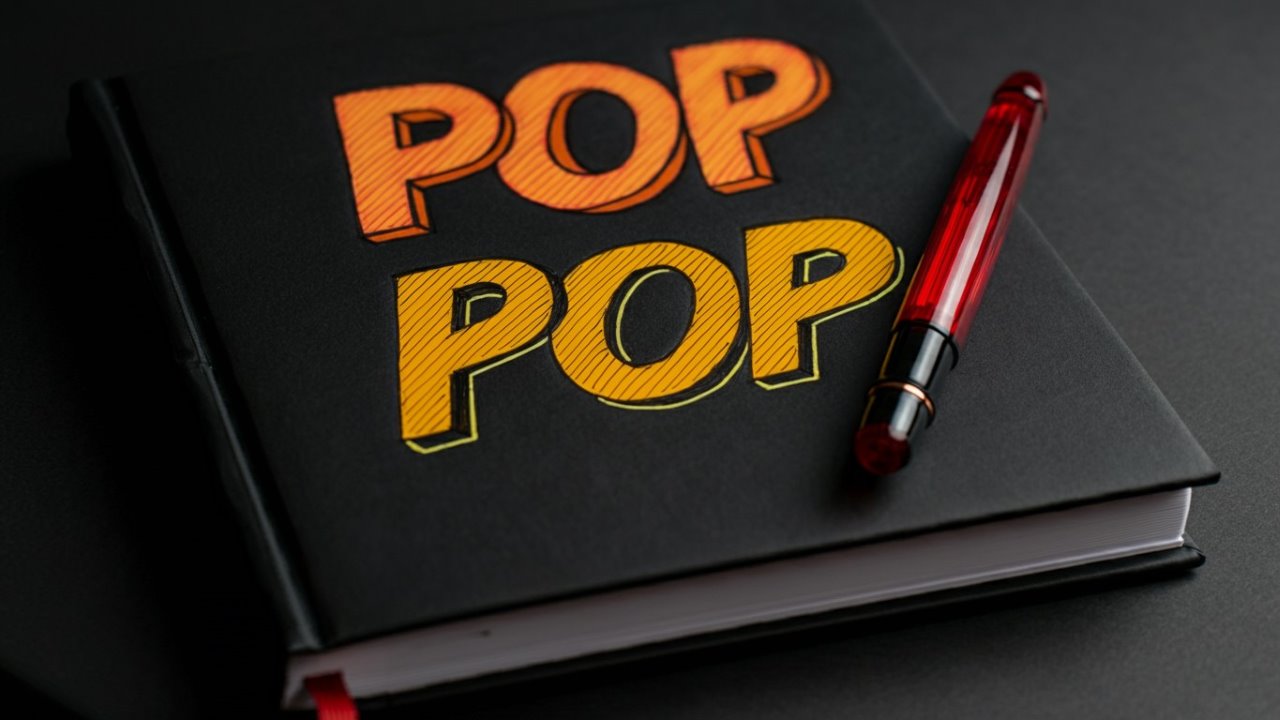
歌はボーカリストがメロディーと歌詞を自分の解釈でまとめあげて「ひとつの世界を作り上げる」と「作詞の基礎講座 04 〜言葉の響きとインパクト〜」で書きました。
作詞した曲を自分で歌うプロのシンガーソングライターや、作詞を兼ねるプロのボーカリストは自分がその歌詞で歌うことを想定して作詞するので「作詞の基礎講座 06 ~効率的な作詞と譜割り変え~」で書いた「ラ・ラ・ラ〜」というフレーズに「ラ・ララ・ラ〜」というように譜割りを変える作業が非常に上手です。
そのことを踏まえながら、今回の作詞の基礎講座 07では「シンガーソングライターの作詞」「形式へのこだわり」「良く聴こえる言葉の音の把握」「ボーカリストのイメージに合った歌詞」について書きたいと思います。
シンガーソングライターの作る歌詞
シンガーソングライターならではの表現
作詞した曲を自分で歌うシンガーソングライターの強みは、何と言っても、自分で歌いながら楽曲制作をすることができるというところです。
優れたシンガーソングライターのなかには、曲と歌詞を作る過程で早口言葉を駆使したボーカル法で、言葉の数合わせではなく、わざと字余りを意識して歌詞を作ったりもします。
少し極論的な例かもしれませんが、200万枚を超えるセールスを記録したMr.Childrenの「名もなき詩」の2コーラスが終わった後の、間奏あけの「成り行きまかせの〜」というところからの早口になる4小節がありますが、これはまさに自分で曲と詞を作りながら歌うシンガーソングライターならではの表現です。
作曲と作詞の担当者が違う楽曲の場合は、まず思いつきもしないフレーズだと言っても過言ではありません。
この4小節は16分音符の連続で、息をつく間もなく言葉が隙間なく埋まっています。1つの16分音符のなかに2つの音が入っている箇所もあり、この箇所を聞いたときにハッとさせられたリスナーも多いのではないでしょうか。
シンガーソングライター 桜井和寿
Mr.Childrenの桜井和寿さんが日本の音楽界を代表する優れたボーカリストであり、作詞家であり、作曲家であるということは、CDセールスや数々の名曲を残した実績を見ても、説明は不要だと思いますが、「名もなき詩」の早口になる16分音符の連続の4小節のインパクトはまさに衝撃的でした。
また、早口の4小節で押した後のフレーズ「誰かを〜つきささる」では、ある程度、音の隙間を空けて、引くことによりしっかりとメリハリをつけて、完全にリスナーを曲のなかに引き込んでいます。
この辺りがシンガーソングライターである桜井さんのすごいところであり、長い間、Mr.Childrenが第一線で活動を続けている大きな要因の一つではないでしょうか。
「名もなき詩」をはじめて聴いたのは和久井映見さん主演のドラマでだったと思いますが、当時、桜井さんの感性とヒラメキに感銘を受けたことを今でも覚えています。また「終わりなき旅」も和久井映見さん主演のドラマの主題歌だったと思います。
ドラマの視聴率が伸び悩んだということもあると思うのですが「終わりなき旅」という曲があまりに素晴らしかったので「ドラマの内容を最後は曲のほうに近づけて行った」というようなコメントを、このドラマの製作スタッフが残していたことが記憶として今でも残っています。
形式へのこだわり
合わなければ修正すれば良い
「シンガーソングライターならではの表現」で触れた、Mr.Childrenの桜井和寿さんの曲を作るプロセスはわかりませんが、ここで、ひとつ言いたいことはシンガーソングライターは「メロディー先行での作詞」とか「ハメコミ」というような形式には、それほどこだわってはいないということです。
自分の作った歌詞にメロディーが付くと思っていた初心者の作詞家志望の方のなかにはメロ先での作詞が上手く行かず「言葉数が合わない」「言葉とメロディーの絡みが悪い」などで悩んでいる方も多いと思いますが、シンガーソングライターは楽曲を制作して行くプロセスのなかで、「合わなければメロディーか歌詞のどちらかを修正すれば良い」というようなスタンスで曲を完成させて行きます。
適当な言葉を使いながらメロディーを作るなかで、適当に口ずさんだ言葉が、あまりにピッタリ来るので、そのまま採用するということも良くある話です。
作詞も手掛ける作曲家の場合
それほど形式にこだわってはいないのは、シンガーソングライターだけではありません。作曲と作詞を自分でする作編曲家も同様に詞先やメロ先といった形式には、それほどこだわりを持っていません。
もちろん現在のポピュラーミュージックの世界で詞先で作って行く作曲家というのは、ほとんどいませんが、あまりにメロディーと歌詞の絡みが悪い場合は「サビの作詞と譜割り変え」で書いた「譜割り変え」以上の修正をして行きます。
ただし、シンガーソングライターと自ら作詞も手掛ける作曲家の楽曲制作では決定的に違うところがあります。
何が違うのかと言うと、作詞も手掛ける作曲家は曲を歌うボーカリストを想定しているところです。
言うまでもなく、作曲家が自分で歌ったものがリリースされる訳ではないので、絶えず自分の楽曲を歌うボーカリストのことを考えながらメロディーと歌詞を作って行きます。
良く聴こえる言葉の音の把握

リスナーに良く聴こえる言葉の音
世の中にはたくさんのボーカリストが居て、その特徴も人それぞれですが、多くのリスナーに受け入れられたシンガーソングライターや作詞を兼ねるボーカリストは、自分の声の特徴やセールスポイントでもあるリスナーに良く聴こえる言葉の音であったりNGな言葉の音を良く知っています。
自ら作詞をする倉木麻衣さんや、浜崎あゆみさんをはじめとするボーカリストたちは、リスナーを引きつけなければならないサビであったり、ロングトーンの箇所では、上記したことを意識して、実際に歌いながら(口ずさみながら)、言葉の響きであったりピッチの良し悪しを確認しながら作詞をしていると思います。
もう少し分かりやすく説明すると、もちろん、それほど気にしていないボーカリストもいますが、曲のサビで高音が伸びるリスナーが聴いていてグッとくる1番オイシイとされるキーや、サビの終わりの音を伸ばす箇所で、自分が得意な母音やピッチが安定しない母音を完全に把握しているということです。
1番オイシイとされるキー
上記した「1番オイシイとされるキー」は、サビのトップキーとその前後が多いです。作曲家もボーカリストの声とボーカル法を最大限に活かそうと、サビのトップキーをどこに持って行くのかということや、トップキーまでのプロセスをフレーズ単位ではなく1音単位でメロディーを作るときに考えて行く人が多いです。
そのため作詞オンリーの方も、それぞれのボーカリストによりグッとくる1番オイシイとされる高音での得意な母音も違うので、作詞をするときには歌詞の内容はもちろんのこと、良く聴こえる言葉の音なども意識して、そのボーカリストに合った歌詞を作らなければなりません。
ボーカリストのイメージに合った歌詞
「商業=プロ」という観点
すでに書く必要はないかもしれませんが、発注者の意向と関係なしに自分の書きたいことを好き勝手に作詞をするというのは「商業=プロ」という観点から切り離せば、一人の表現者という点では良い作詞家かもしれません。
もちろん自分の作りたいものを作るというのが、作詞に限らず「何かを作品にする」ということの始まりです。
しかし「作詞の基礎講座 01」でも書きましたが、相手があってのものなので、そのスタンスで歌詞を作り続けても「商業=プロ」という観点からみると三流、もしくは、それ以下の作詞家としか認識されず、決め打ちで仕事を発注してもらえる可能性は限りなく低いです。
一般リスナーと同じ目線に立つ
ボーカリストのイメージに合った歌詞を作るのは、一般リスナーと同じ目線に立てば、けして難しいことではありません。
もし面識がないボーカリストの作詞を依頼されたときは、過去にリリースされたそのボーカリストの曲を参考にして、そのボーカリストに対して自分が持っているイメージに沿って、「この人にこの歌詞を歌ってもらいたい」「この人には、この歌詞がピッタリだ」というような感じで歌詞を作って行けば良いのです。
上記したことで一つ例を出すと、あまり良い例ではないかもしれませんが、酒井法子さんの不祥事によって、2009年に再度話題になった「碧いうさぎ」などが参考になるのではないでしょうか。
この楽曲の作詞家である牧穂エミ さんの「彼女の曇り一点なく純粋なイメージ」を歌詞にしたという作品に関してのコメントが印象に残っている方もいると思います。
方向性を変える場合
発注者の希望で「今までの作品と方向性を変えたい」という要望や、作詞家に発言力がある場合は「自ら思い切ってボーカリストの歌詞の方向性を変えたい」という状況も、長く作詞家をやっていればあると思います。
ここで重要なのは「何を目的に変えるのか」というコンセプトを明確にすることです。まだ駆け出しの作詞家や、コンペなどのチャンスをもらい、これから上へ登って行こうという作詞家の場合は、まずは歌詞のテーマとともにコンセプトを明確にしなくてはいけません。
そして、その人が歌っている姿を想像して「格好良いか?格好悪いか?」や「おかしいか?おかしくないか?」などを考えながら作詞して行く必要があります。
すでに作詞家に発言力のある後者の場合は、すでにプロデューサー的な視点も充分に持っているので、あえて書く必要はないと思います。